2025年7月15日、静岡県伊豆市の日本サイクルスポーツセンター内「サイテル」にて、
日本競輪選手会様の新人選手研修にてアンチドーピングセミナーを実施させていただきました。
今回の研修では、座学の講義とともにカードゲーム「ドーピングガーディアン」の体験を組み合わせ、
アンチドーピングを“ルールとして覚える”のではなく、“自分自身と競技を守る手段として理解する”ことを目指しました。

知識より前に伝えたい「意味」と「価値」
今回は、個別の禁止物質の名前や細かいリストを教えることが目的ではありませんでした。
それよりも、まず選手に伝えたかったのは、
アンチドーピングは「自分を守る知識」であり、「競技の価値を守る意識」であるということです。
違反を避けるための制度というより、
選手全員が共通の“前提”を持って競技に臨むことで、公正さと安全が担保される──
そんな“文化としてのアンチドーピング”の大切さに、まず触れてもらいたいと考えました。
疑似体験で「うっかり」を“自分ごと”に
ドーピングガーディアンでは、選手がアスリート役となって試合に向けて体調を整え、
薬やサプリメントの使用を選択しながら進んでいきます。
「知らずに使った風邪薬が実は禁止だった」「症状を我慢すれば出場できたのか」など、
現実でも起こりうるような場面設定の中で、自分ならどうするか?と考えながら体験できます。
ゲーム中には笑いや驚きもあり、場の雰囲気は明るいものでしたが、
進行とともに選手たちの表情が徐々に真剣に変わっていくのが印象的でした。

ゲームだからこそ伝わる“迷い”と“相談”
「これって違反になる?」「大丈夫って言われたけど信じていいの?」
実際のプレイ中には、そうしたリアルな迷いの声があちこちで聞こえてきました。
その疑問に答えながら、
「不安に思ったら相談できる環境を整えること」、
「周囲のスタッフや専門家を味方につけること」が選手自身の権利であることを伝えました。
私は今回、ゲームを通じて選手との距離が縮まったように感じました。
「スポーツファーマシストって、もっと気軽に相談していい存在なんだ」
と感じてもらえたのなら、それだけでも大きな成果だったと思います。
知識は共有されてこそ力になる
講義の中では、禁止物質の基礎だけでなく、
サプリメントリスク、申請制度、ネット情報の落とし穴など、
選手生活の中で陥りやすいポイントを取り上げました。
ただし、知識は“個人の武器”としてではなく、
選手全体で共通認識を持つことで初めて、安全と公平性を支える力になります。
だからこそ、チーム全体でアンチドーピングへの理解を深め、
「おかしいな」と思ったときに相談し合える文化を根づかせていくことが必要です。

講演、執筆、ドーピングガーディアン体験会随時受付中!
スポーツ団体、教育機関、行政機関、薬剤師会などアンチ・ドーピング講座やドーピングガーディアン体験会などのご依頼はお気軽にお問い合わせください。
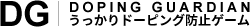



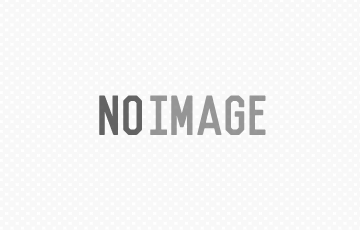






コメントを残す